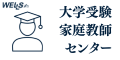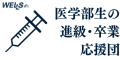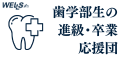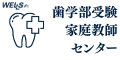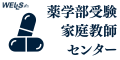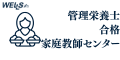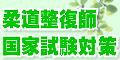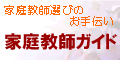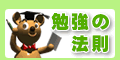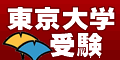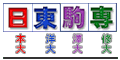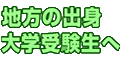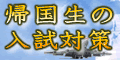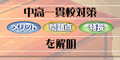【獣医学部 予備校】生活リズムの立て直しから始まった合格までの一年——予備校でつまずいたTくんの再スタート
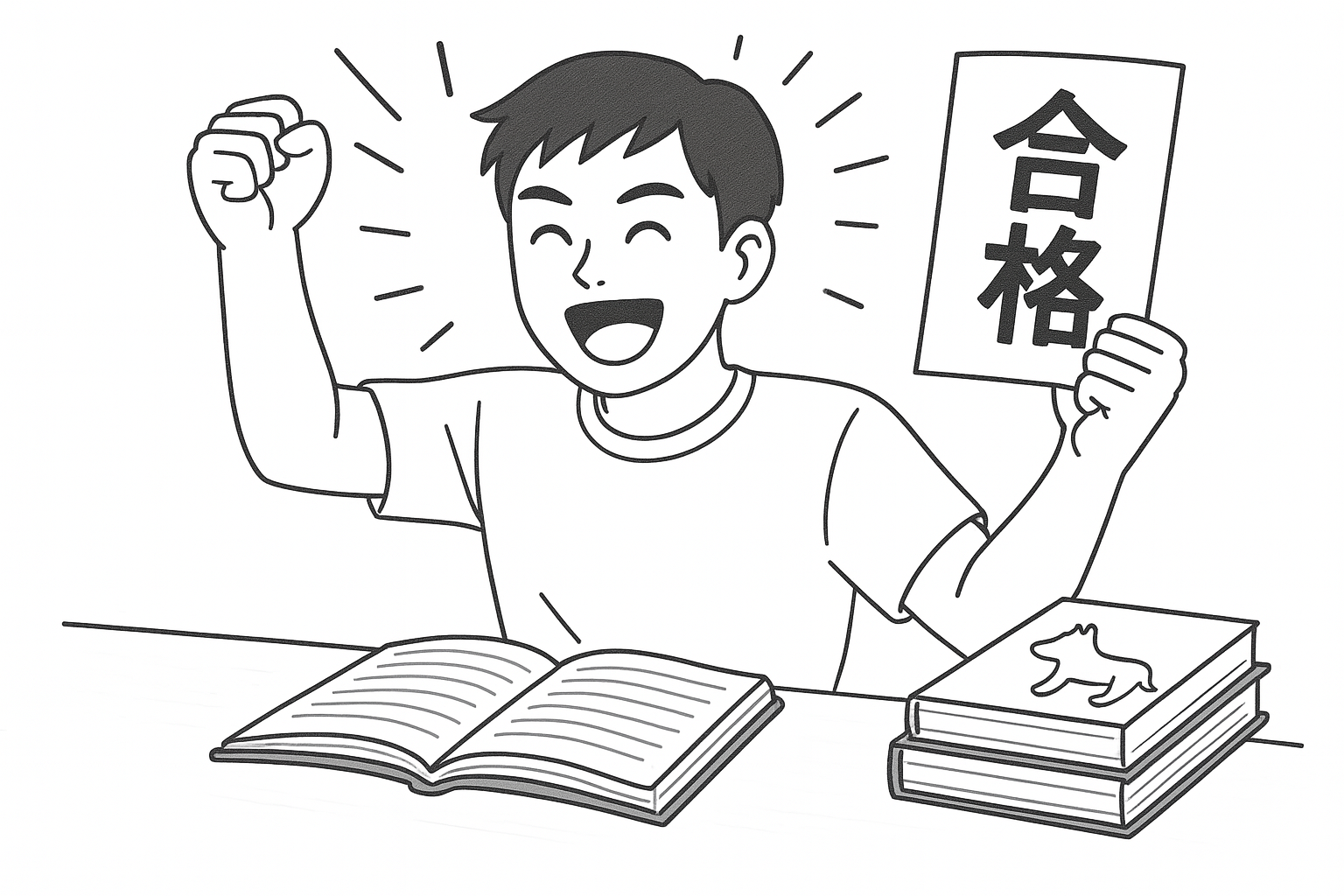
予備校生活の現実!崩れていった生活と失われた目標意識
Tくんが家庭教師の指導を受けることに決めたのは、予備校での1年間を振り返り、「このままではダメだ」と感じたからでした。高校卒業後、浪人生活を始めた当初はやる気に満ちていたと言います。しかし予備校通いが始まってすぐに、生活が徐々に崩れていきました。朝起きるのがつらく、遅刻が増え、たまには授業をさぼってしまうこともあったそうです。理由ははっきりしていて、夜遅くまでスマートフォンを見たり、だらだらと勉強しているようで実は中途半端に終わっていたりと、生活のリズムそのものが乱れていたのです。
自習の毎日。「今日は何をやろうか」で終わる不安定な勉強
自習室を活用することもあったそうですが、勉強の内容は毎日その場しだいで、「今日は何をしようか」と考えているうちに一日が終わってしまうこともしばしば。目標があいまいなまま、どこかに「なんとかなるだろう」という甘えがあったと、後になってTくん自身が語っていました。そして予備校に通う意味すら見いだせなくなっていき、気づけば、最初に思い描いていた「志望校合格」という目標も遠のいていきました。
「このままではダメだ」家庭教師という選択で再スタート
そんな自分を変えるきっかけとなったのが、「家庭教師で受験する」という選択でした。再び同じような1年を過ごすわけにはいかないと痛感していたTくんは、今度は「勉強だけでなく生活そのものを見直したい」という思いで、家庭教師の指導を受けることにしました。
初回の面談で告げた悩み「朝起きるのが本当に苦手なんです」
初回の面談で教師に伝えたのは、「まず朝起きることが本当に苦手なんです」という率直な悩みでした。
指導が始まった当初は、やはり朝がつらく、決めた時間に起きられないこともしばしばありました。
勉強だけじゃない。生活習慣から支える家庭教師の伴走
しかし教師は勉強の指導だけでなく、生活習慣そのものに目を向けてくれました。年間スケジュールと日々のルーティンを一緒に組み立て、具体的に「何時に起きて」「何時にどの科目をやるか」という時間割を作成。守れなかったときには、理由を分析し、どうすれば改善できるかをその都度話し合いました。
厳しさも本気の証!甘えを排除してくれた「外の視点」
時には、教師から厳しく指摘されることもあったようですが、それもすべて「本気で向き合ってくれている」とTくんは感じていたと話しています。何より大きかったのは、自分の勉強に“客観的な視点”が加わったことです。自分だけで考えていると、甘えも入り込みます。
毎日のルーティン作りと、できなかった日の“振り返り習慣”
しかし、毎週の授業での進捗確認や学習計画の見直しを通して、「これは今週やると決めたこと」「これはまだできていないこと」が明確になり、徐々に自分の中でも“やらなければならないこと”が形を持って見えるようになっていきました。
朝起きるだけで苦しい日々。小さな約束を守り続けた積み重ね
生活リズムも、最初は苦労の連続でした。朝は頭がぼんやりして、集中力も続かず、決めたスケジュールが思うようにこなせない日も多かったと言います。それでも、「まずは起きる時間だけは守る」「眠くても机に向かう」というルールを自分に課し、毎日、同じ時間に起きることから習慣づけました。すると、1ヶ月、2ヶ月と経つうちに、少しずつ身体が慣れ、自然と起きて行動を始められるようになってきたそうです。
起きる・動く・集中する。リズムの中で変わっていく学習効率
生活にリズムが生まれたことで、勉強にも集中できるようになりました。朝は計算問題や英単語の復習、昼には理科や社会の理解型科目、夕方以降には記述や演習問題と、1日の流れが固定されたことで、学習効率も上がり、本人も「今までで一番勉強が身についていると感じた」と言っていました。
模試結果から「今やるべきこと」を見える化して修正を重ねる
教師との面談では、模試の結果をもとに次の課題を洗い出し、「今の自分に必要なこと」を明確にし続けました。
「去年の自分を繰り返さない」生活改善がもたらした合格
そして1年後、迎えた本番の受験。無事、第一志望の大学に合格し、晴れて春を迎えることができました。合格を報告してくれたTくんの言葉はとても印象的でした。「結局、合格につながったのは生活を整えたことだと思います。去年の自分を絶対に繰り返さないと、1年間ずっと自分に言い聞かせてきたことが、ちゃんと力になっていたんだと、今しみじみ感じています。」
合格の先に見えた、“生き方を整える”という受験の本質
この一年、Tくんは“勉強のやり方”だけでなく、“生き方の姿勢”そのものを変えていきました。規則正しい生活を自分で築く力、誰かの支えを借りながらも自分の行動に責任を持つ力。それこそが、彼を合格へと導いた最大の要因だったのだと思います。受験は単なる知識の勝負ではなく、日々の習慣の積み重ねであることを、彼の姿が教えてくれました。